【重要】自ら申請しないと連絡がない場合もありますので注意が必要です。

#税金 #TAX #定額減税 #不足額給付金 #調整給付金
- 「不足額給付金」制度の目的
- 給付の対象者
- 定額減税の不足が生じた方(不足額給付1)
- 定額減税の対象外であった方で、かつ、低所得世帯向け給付の対象にもならなかった方(不足額給付2)
- 給付額
- 申請・支給時期
- 留意事項
- 行政から連絡がない場合もありますので注意!
- 参考
- 【Review】 定額減税について
- Note(ノート)
- 【Review】
- 所得税と住民税の計算の仕方 & 年金受給者・自営業者の配当控除の注意点(令和6年度改正対応版)
- まとめ & 注意点(令和6年度改正対応)
- 住民税のしくみ
- 所得税のしくみ
- 103万円の壁:所得税が発生するライン
- 108万円の壁:住民税が発生するライン
- 130万円の壁:社会保険加入義務のライン
- 150万円の壁:対象は配偶者控除の影響
- 各壁の影響の違い
- 壁のまとめ【103万円・108万円・130万円・150万円】
- 住民税非課税世帯とは?
- 基礎控除について
- 公的年金等控除とは?
- 住民税の申告制度とは?
- 所得税の確定申告が終了した後、申告された内容が市町村に住民税等の計算に必要な数値として通達される時期
- 国民健康保険料の金額は、住民税の決定より前に、ある程度の目安を知ることができます。ただし、正確な金額は住民税の決定後となります。
- 【おさらい】年金から天引きされるもの
- 年金の「155万円の壁」と「211万円の壁」とは
- 国民健康保険計算機
- 年金の繰上げ受給について
- 確定申告(e-TAX)
- 税務署【国税庁】
- デジタル庁
- 株を始めましょう (新NISAで益々有利に)
- お勧め書籍
- 北の大地十勝
「不足額給付金」制度の目的
2025年7月より始まる「不足額給付金」(定額減税4万円)について、
現在の情報をもとに詳しく説明します。
制度の目的
この給付金は、2024年に実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円、計4万円)において、税額が少なく定額減税を十分に受けきれないと見込まれる方、または、2024年の当初の給付金算定時に予測された税額と、実際に確定した税額との間に差が生じた方などに対し、その不足分を補うことを目的としています。
給付の対象者
主に以下のいずれかに該当する方が対象となります。
給付金の詳細は、お住まいの市区町村のウェブサイトや広報等で確認してください。自治体によって通知の発送時期や申請方法、支給時期が異なります。
この情報は現時点での一般的な概要であり、個別の状況や各自治体の判断により異なる場合がありますので、必ずお住まいの市区町村の情報を確認してください。
定額減税の不足が生じた方(不足額給付1)
2024年分の所得税および定額減税の実績が確定した結果、本来受けられるべき定額減税額に不足が生じた方。
具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
2024年中の所得が2023年中に比べて減少した(退職、育休など)ため、2024年分の所得税額が当初の推計額を下回った場合。
2024年中に子どもの出生などにより扶養親族が増加したため、所得税分の定額減税可能額が当初の計算より増えた場合。
当初の調整給付後に税額修正が生じ、2024年度分の個人住民税所得割額が減少した場合。
定額減税の対象外であった方で、かつ、低所得世帯向け給付の対象にもならなかった方(不足額給付2)
2024年分の所得税および2024年度個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円(つまり本人として定額減税の対象外)である方。
税制度上「扶養親族等」の対象外となる方(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方など)。
自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税額・住民税所得割額が0円)方で、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向けの給付の対象とならなかった場合。
本人の年金等の合計所得金額が48万円を超えるため、納税者(子など)の扶養親族にならず、かつ自身に所得税・住民税所得割が課されない方で、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向けの給付の対象とならなかった場合。
給付額
原則として、不足が生じた額(最大4万円)が給付されます。ただし、ケースによっては金額が異なる場合があります
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となることがあります。
令和5年または6年に税制度上扶養親族の対象外であるという要件により、給付額が減額されることがあります(例:令和5年のみ該当で1万円、令和6年のみ該当で3万円など)。
申請・支給時期
多くの自治体では、2025年7月下旬以降に順次通知が発送される予定です。
支給開始時期は、多くの自治体で2025年8月頃を予定していますが、自治体によって異なります。
「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要で、指定の口座(前回の給付金受給口座や公金受取口座など)に振り込まれます。
「支給確認書」が届いた方や、対象となる方で2024年1月2日から2025年1月1日までに転入した方は、手続き(申請書の提出)が必要となる場合があります。
申請期限は、多くの場合、2025年10月31日頃までとされていますが、自治体によって異なるため、お住まいの自治体の情報を確認することが重要です。
留意事項
本給付金は、差押禁止および非課税所得となります。
給付金額は、原則として2025年6月2日時点の賦課資料(確定申告等)に基づき計算されるため、それ以降の賦課資料の修正等による金額変更は原則できません。
行政から連絡がない場合もありますので注意!
- 「支給のお知らせ」が届く場合(原則、手続き不要)
- 自治体が給付金の対象者であることを把握しており、かつ、過去の給付金事業などで振込口座の情報を把握している場合に送付されます。
- このお知らせが届いた場合、原則として申請手続きは不要です。記載された口座に自動的に給付金が振り込まれます。
- ただし、口座を変更したい場合や、給付金の受給を辞退したい場合は、別途手続きが必要となることがあります。
- 「支給確認書」や「制度案内はがき」が届く場合(手続きが必要)
- 自治体が対象者である可能性を把握しているものの、振込口座の情報がない場合や、受給の意思を確認する必要がある場合に送付されます。
- この書類が届いた場合は、記載された申請方法(オンライン申請や書類の返送など)で手続きを行う必要があります。手続きをしないと給付金は支給されません。
- いずれの書類も届かない場合(ご自身で申請が必要な可能性あり)
- 自治体が対象者であることを把握できていない場合や、2024年1月2日以降に転入した方など、現在の自治体で以前の自治体での所得状況や当初給付金の受給状況を把握できない場合には、お知らせや確認書が自動的に発送されないことがあります。
- この場合、ご自身が給付金の対象となる可能性があるにもかかわらず書類が届かない場合は、ご自身で自治体に問い合わせ、申請を行う必要があります。
まとめ
行政からのアプローチはありますが、その内容によって手続きの要不要が変わります。特に「支給確認書」が届いた場合や、何も届かない場合は、ご自身での手続きや問い合わせが必要となる可能性があります。お住まいの自治体のウェブサイトや広報誌などで、詳細な情報を確認することをお勧めします。
参考

札幌市HP
【Review】 定額減税について
定額減税とは
定額減税とは、物価高騰による国民の負担を緩和するため、政府が実施する一時的な税負担軽減策です。所得税と住民税から一定額を差し引くことで、実質的な手取り額を増やすことを目的としています。
実施の背景と目的
- 物価高騰対策: ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響などにより、食料品やエネルギー価格を中心に物価が高騰し、家計を圧迫しています。
- 所得の伸び悩み: 物価が上昇する一方で、賃金の上昇が追いつかず、実質賃金が減少傾向にあります。
- 経済の好循環創出: 国民の可処分所得を増やすことで、消費を喚起し、経済全体の好循環を生み出すことを目指しています。
定額減税の対象と減税額(2024年実施分)
2024年に実施された定額減税の主な内容は以下の通りです。 - 対象者:
- 納税者本人(居住者であること)
- 同一生計配偶者
- 扶養親族
- いずれも合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下に相当)の者
- 減税額:
- 所得税: 1人あたり 3万円
- 住民税: 1人あたり 1万円
- 合計: 1人あたり 4万円
例えば、納税者本人と扶養親族2人の世帯の場合、合計で12万円(4万円 × 3人)の減税となります。
定額減税の実施方法
定額減税は、給与所得者と年金所得者、個人事業主で実施方法が異なります。 - 給与所得者の場合(原則、手続き不要)
- 所得税: 2024年6月以降の給与や賞与から天引きされる源泉徴収税額から順次減税されます。
- 例えば、6月の給与の源泉徴収額が減税額に満たない場合は、7月以降の給与や賞与に繰り越して減税が適用されます。
- 年末調整で最終的な調整が行われます。
- 住民税: 2024年6月分の住民税は徴収されず、2024年7月~2025年5月までの11ヶ月間で均等に減税された額が徴収されます。
- 年金所得者の場合(原則、手続き不要)
- 所得税: 2024年6月以降の年金支給時に、源泉徴収税額から減税されます。
- 住民税: 2024年10月以降に支給される年金から、住民税が減税されます。
- 個人事業主の場合(確定申告で手続きが必要)
- 2024年分の所得税の確定申告(2025年3月提出)において、所得税から減税されます。予定納税がある場合は、第1期分(2024年7月)から減額されます。
- 住民税は、2025年6月以降に送付される住民税の通知書で減税後の税額が反映されます。
減税しきれない場合の対応(調整給付金・不足額給付金)
定額減税は税額から差し引くため、所得税や住民税の納税額が少ない方(例えば、もともと税金がかからない方や少額の方)は、減税額の恩恵を十分に受けられない可能性があります。
このため、以下の措置が取られています。 - 調整給付金(2024年夏頃から実施):
- 定額減税で引ききれなかった所得税額と住民税額の合計額を1万円単位で切り上げて給付するものです。
- 例えば、合計で3万5千円の減税効果しか得られなかった場合、切り上げて4万円が給付されます。
- 不足額給付金(2025年7月以降に実施):
- 2024年の定額減税実施後、実際の所得や税額が確定した際に、当初の想定よりも減税額が不足した方や、もともと所得税・住民税が課されず調整給付金の対象外であった方などを対象に、不足分を補填する給付金です。
- この制度は、前述の「2025年7月より始まる不足額給付金」にあたります。
注意点 - 定額減税は一時的な措置であり、永続的な制度ではありません。
- 減税額は、あくまで税金からの控除であり、給付金とは異なります。ただし、減税しきれない場合は給付金で補填されます。
- 具体的な適用方法や支給時期、不明点については、お住まいの自治体や国税庁のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。
この定額減税は、物価高騰に直面する国民の生活を直接的に支援するための重要な政策の一つとなっています。
Note(ノート)

【Review】
所得税と住民税の計算の仕方 & 年金受給者・自営業者の配当控除の注意点(令和6年度改正対応版)
【税金TAX】所得税と住民税の計算の仕方 & 年金受給者・自営業者の配当控除の注意点(令和6年度改正対応版)
令和6年度(2024年度)から、「住民税のみ申告不要」が廃止!
これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなりました。
特に、配当所得を申告する際の影響が大きいため、慎重な判断が必要です。
🔹 1. 所得税と住民税の基本的な違い
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 税率 | 累進課税(5%~45%) | 一律10%(一部非課税) |
| 計算方法 | 課税所得 × 税率(累進) | 課税所得 × 10%(均等) |
| 控除 | 医療費控除、配当控除 など | 基本的に所得税と同じ |
| 改正点 | 配当所得の申告方法が住民税と統一 | 「住民税のみ申告不要」が廃止 |
🔹 2. 配当所得の課税方法と選び方
配当金を受け取った場合、次の3つの課税方式 から選択できます。
ただし、令和6年度からは、所得税と住民税で別々の方式を選べなくなった ため、慎重な選択が必要です。
| 課税方式 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 総合課税(配当控除あり) | 他の所得と合算し、累進課税 | 配当控除が適用され、所得税が軽減される | 所得が増えると税率UP&住民税・健康保険料が増加 |
| ② 分離課税(税率20.315%) | 配当金を他の所得と分けて課税 | 税率が一定(20.315%)なので高所得者に有利 | 配当控除が使えない |
| ③ 申告不要 | 確定申告せず、源泉徴収(20.315%)のみ | 手続き不要でシンプル | 配当控除が使えない&税金が最適化できない |
🔹 3. 年金受給者・自営業者の配当控除の注意点
✅ 年金受給者
• 年金収入が少なく、所得税率が低い場合 は、「総合課税+配当控除」 を選ぶと有利。
• ただし、総合課税にすると住民税や健康保険料が増加するリスク あり。
• これまで可能だった「住民税だけ申告不要」は 令和6年度から廃止 されたため、所得税・住民税の両方で配当所得の課税方法を統一する必要あり!
🔹 例:年金収入200万円+配当所得50万円
→ 総合課税なら配当控除で所得税が軽減できるが、住民税も増える可能性がある。
→ 分離課税なら税率20.315%固定で、健康保険料への影響を抑えられる。
✅ 自営業者
• 所得が低い場合は、総合課税+配当控除を活用すると有利。
• 所得が高い場合は、分離課税(20.315%)を選ぶほうが税負担が軽いことが多い。
• 令和6年度以降、住民税の課税方式が統一されたため、住民税負担も考慮して選ぶ必要がある!
🔹 例:事業所得500万円+配当所得100万円
→ 総合課税を選ぶと、税率が上がるため分離課税のほうが有利。
→ 住民税でも同じ課税方式になるので、分離課税を選ぶと住民税負担も一定にできる。
🔹 4. 令和6年度の改正点:「住民税のみ申告不要」が廃止!
💡 今までは…
✅ 所得税では「総合課税」を選び、配当控除を適用して節税
✅ 住民税では「申告不要」を選び、住民税負担(10%)を回避
✅ この組み合わせで税負担を最小限にできた!
💡 これからは…
❌ 所得税と住民税で別々の課税方式を選べなくなった!
❌ 所得税で「総合課税」を選ぶと、住民税も強制的に総合課税に
❌ 住民税で「申告不要」を選ぶには、所得税でも「申告不要」にする必要あり
➡ 節税戦略が大きく変わるので要注意!
🔹 5. どの課税方式を選ぶべきか?(改正後の最適な選択)
| 所得の種類 | 適した配当所得の申告方法(令和6年度以降) |
|---|---|
| 年金受給者(低所得) | 総合課税+配当控除(住民税増加に注意) |
| 年金受給者(高所得) | 分離課税(税率一定&住民税対策) |
| 自営業者(低所得) | 総合課税+配当控除(住民税負担を考慮) |
| 自営業者(高所得) | 分離課税(累進課税の影響を避ける) |
🔹 6. まとめ & 注意点
✅ 所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなった!
✅ 配当所得の申告方法は「総合課税」「分離課税」「申告不要」から統一的に選ぶ必要あり!
✅ 総合課税は配当控除のメリットがあるが、住民税・健康保険料の負担増に注意!
✅ 所得が高い場合は、分離課税(20.315%)のほうが有利なことが多い!
✅ これまでの節税方法が使えなくなるため、確定申告時に慎重に選択すべし!
🔍 結論:新ルールに対応した賢い申告を!
令和6年度からの改正により、今までの節税策が通用しなくなりました。
特に配当所得がある方は、所得税と住民税を一緒に考えて、最適な方法を選ぶことが重要です!
「総合課税で配当控除を受けるか?」
「分離課税で税率を一定にするか?」
➡ 新ルールを理解し、自分に合った最適な申告方法を選びましょう!
まとめ & 注意点(令和6年度改正対応)
令和6年度から「住民税のみ申告不要」が廃止され、所得税と住民税の課税方式を統一する必要があります。
この変更により、配当所得や株式譲渡益のある人の税負担が変わる可能性があるため、確定申告時に慎重な選択が求められます。
✅ 注意点①:所得税と住民税で異なる課税方式を選べない!
📌 これまで(令和5年度まで)
✔ 所得税では「総合課税」を選び、配当控除を適用して節税
✔ 住民税では「申告不要」を選び、住民税の負担(10%)を抑える
✔ この組み合わせにより、所得税と住民税のバランスを最適化できた
📌 これから(令和6年度以降)
❌ 所得税と住民税で異なる課税方式を選べない!
❌ 所得税で「総合課税」を選ぶと、住民税も総合課税になる
❌ 所得税で「分離課税」を選ぶと、住民税も分離課税になる
❌ 所得税で「申告不要」を選ぶと、住民税も申告不要になる
➡ 住民税の負担を抑えるために「住民税だけ申告不要」にする節税策が使えなくなった!
✅ 注意点②:「総合課税+配当控除」は本当に得か?
配当所得がある人は、「総合課税+配当控除」を選べば、所得税が軽減される というメリットがあります。
しかし、総合課税にすると、住民税や健康保険料が上がるリスク があるため要注意!
📌 配当控除のメリット
• 所得税が軽減される(税率が低い人ほど有利)
• 配当金と他の所得を合算できる
📌 総合課税のデメリット
❌ 住民税が増える(累進課税の影響)
❌ 国民健康保険料・介護保険料・高額療養費の負担増のリスク
➡ 年金受給者や低所得者は「総合課税+配当控除」で得する場合もあるが、住民税や保険料の増加に注意! (住民税非課税世帯の方は解除になる場合があります!)
✅ 注意点③:「分離課税」が有利なケースもある!
配当所得がある場合、「分離課税」を選べば、税率が一定(20.315%) なので、
特に所得が高い人 や 住民税・健康保険料の負担を抑えたい人 には有利な選択肢になることも!
📌 分離課税のメリット
✔ 税率が一定(20.315%)なので、高所得者に有利!
✔ 住民税や健康保険料に影響を与えにくい!
✔ 所得が増えても累進課税の影響を受けない!
📌 分離課税のデメリット
❌ 配当控除が使えない(所得税の軽減なし)
❌ 低所得者は総合課税のほうが有利な場合も!
➡ 「総合課税で配当控除を受けるか?」「分離課税で税率を固定するか?」を慎重に判断する必要がある!
✅ 注意点④:「申告不要」にすると得するのか?
「申告不要」を選ぶと、配当金に対して源泉徴収された20.315%の税金をそのまま納めることになる ので、
✔ 手続きが不要で楽 というメリットはあるが、
❌ 所得税・住民税を最適化できない というデメリットもある。
特に、令和6年度から「住民税のみ申告不要」ができなくなったため、節税効果は低くなる可能性が高い。
➡ 所得税・住民税の両方を考慮した上で、「総合課税」「分離課税」と比較して判断が必要!
✅ 注意点⑤:医療費控除・配当控除など還付申告は早めに!
• 医療費控除や配当控除などの還付申告は、確定申告の開始を待たずに行える!
• 早く申告すれば、その分早く還付金を受け取れるため有利!
• 還付申告は5年間有効なので、過去の控除漏れがある場合も確認すると良い!
📢 まとめ:確定申告時に考えるべきポイント
✅ 所得税と住民税で別々の課税方式を選べなくなった!
✅ 配当所得の申告方法は「総合課税」「分離課税」「申告不要」から統一的に選ぶ必要あり!
✅ 総合課税は配当控除のメリットがあるが、住民税・健康保険料の負担増に注意!
✅ 所得が高い場合は、分離課税(税率20.315%)のほうが有利なことが多い!
✅ 住民税のみ「申告不要」にして負担を減らす節税策が使えなくなった!
✅ 医療費控除・配当控除などの還付申告は早めにすると還付金が早く受け取れる!
➡ 令和6年度からの改正で節税方法が変わるため、確定申告時には慎重な選択が必要!
➡ 「総合課税+配当控除」「分離課税」「申告不要」のどれが自分に最適か、事前にしっかり検討しよう!
住民税のしくみ
住民税は、居住する自治体が課税する地方税で、地方自治体が提供する公共サービスの財源となるものです。市区町村民税(市町村税)と道府県民税(都道府県税)の合計から成り立ちます。
1. 住民税の特徴
• 課税対象者:1月1日時点で日本国内の市区町村に住所がある人が対象。
• 納税先:その年の1月1日に住んでいる市区町村に納めます(前年の所得が基準)。
• 課税方法:前年の所得を基準に計算されるため、「前年分課税」とも呼ばれます。
2. 住民税の内訳
住民税は、主に以下の2つで構成されます。
(1) 均等割
• 所得額に関係なく一律で課税される部分。
均等割額の内訳
多くの自治体では、住民税均等割の内訳が「都道府県民税」と「市区町村民税」で異なる割合になっています。ただし、これは基本額であり、自治体によって独自の税率が設定される場合があります。
• 都道府県民税:1,000円
• 市区町村民税:3,000円
• 森林環境税:1,000円(全国一律)
合計:5,000円
東日本大震災に伴う住民税均等割の臨時増額措置(復興支援目的)は、現在では森林環境税に引き継がれる形で廃止されています。
【森林環境税の導入】
森林環境税は森林整備や地球温暖化防止を目的として、全国一律で年間1,000円が課税される税金課されるようになりました。
(2) 所得割
• 前年の所得に応じて課税される部分。
• 税率:
• 市区町村民税:6%
• 道府県民税:4%
• 合計:10%
• 計算式:
所得割 = (課税所得 – 各種控除) × 税率
3. 住民税の計算方法
住民税は以下の手順で計算されます。
(1) 課税所得を求める
課税所得は、総所得から所得控除を引いた金額です。
課税所得 = 総所得金額 – 所得控除額
(2) 所得割を計算
課税所得に税率10%(市区町村民税6%、道府県民税4%)を適用。
(3) 均等割を加算
均等割(5,000円)を加算します。
例:計算例
• 総所得:300万円
• 所得控除:150万円
• 課税所得:300万円 – 150万円 = 150万円
• 所得割:150万円 × 10% = 15万円
• 均等割:5,000円
• 合計:15万円 + 5,000円 = 155,000円
4. 住民税が非課税になる場合
以下の条件を満たすと住民税が非課税となります。
(1) 均等割が非課税になる条件
1. 生活保護受給者
2. 市区町村ごとに定める非課税基準以下の所得
• 扶養家族の人数に応じた非課税限度額以下の場合。
(2) 所得割が非課税になる条件
• 前年の総所得金額が、以下の非課税基準以下の場合。
• 単身者:年収100万円以下
• 扶養親族1人の場合:年収155万円以下
• 扶養親族2人の場合:年収205万円以下
(扶養親族が増えるごとに約50万円の基準が加算)
5. 住民税の納付方法
住民税の納付には以下の方法があります。
(1) 普通徴収
• 自営業者や無職の人が対象。
• 自分で住民税を支払う方法。
• 納期:年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
(2) 特別徴収
• 会社員や公務員が対象。
• 給与から住民税が天引きされる方法。
• 会社が代わりに納付。
6. 住民税の用途
住民税は、住民が受ける行政サービスの財源として使用されます。具体的には以下の分野に充てられます。
• 医療、福祉、教育、道路整備
• 防災、消防、治安維持
• 地域振興など
7. 注意点とポイント
1. 前年分課税:
• 前年の所得が基準になるため、退職や収入減少があっても住民税の負担が続く可能性があります。
2. 年金受給者の場合:
• 公的年金にも住民税が課されることがあります。
3. 非課税世帯を目指す:
• 所得控除を最大限活用することで、住民税非課税世帯の基準を満たすことが可能です。
4. 最新の税制を確認:
• 住民税の税率や非課税基準額は、地方自治体ごとに異なる場合があります。
8. まとめ
住民税は、地域社会を支える重要な税金ですが、控除や非課税基準などを理解することで負担を減らせる可能性があります。自分の所得や控除内容を見直し、必要に応じて自治体に相談することをおすすめします。
所得税のしくみ
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金で、日本では国に納める「国税」に分類されます。所得の種類や金額、控除額などによって計算されます。
1. 所得税の計算方法
所得税は以下の手順で計算します:
(1) 所得金額を求める
所得金額 = 収入(年収) – 必要経費
• 収入:給与や事業収入、不動産収入など、1年間に得た収入全体。
• 必要経費:収入を得るためにかかった費用(給与所得者の場合は「給与所得控除」が適用)。
(2) 課税所得金額を求める
課税所得金額 = 所得金額 – 各種所得控除
• 主な所得控除:
• 基礎控除:48万円
• 配偶者控除、扶養控除:条件により適用
• 社会保険料控除:健康保険料や年金保険料など
• 医療費控除、生命保険料控除、雑損控除など
(3) 税率を適用して所得税額を求める
所得税は累進課税制度(所得が高くなるほど税率が高くなる仕組み)を採用しています。
課税所得金額 所得税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,800万円以下 20% 97万5,000円
4,000万円以下 30% 279万5,000円
6,000万円以下 40% 479万5,000円
6,000万円超 45% 639万5,000円
所得税の最高税率
日本の所得税の最高税率は**45%**です。
これに加え、住民税の税率(通常一律10%)が課されるため、**所得税と住民税を合わせた最高税率は55%**になります。
103万円の壁:所得税が発生するライン
対象:アルバイト・パートなどで収入がある扶養家族
• 年収が103万円以下であれば、所得税が課税されません。
• 所得税の基礎控除額が48万円。
• 給与所得控除が55万円。
• 合計で48万円 + 55万円 = 103万円までは課税対象になりません。
収入が103万円を超えるとどうなるか?
• 自分自身に所得税が課税されるようになります。
• ただし、103万円を少し超えた場合の税額は比較的少額(収入額 × 5%が税額)です。
108万円の壁:住民税が発生するライン
対象:アルバイト・パートなどで収入がある扶養家族
• 住民税の非課税限度額は、多くの自治体で年収100万円~108万円前後です(自治体による差異あり)。
• 基礎控除額:43万円。
• 給与所得控除:55万円。
• 非課税限度額:43万円 + 55万円 = 98万円~108万円程度。
収入が108万円を超えるとどうなるか?
• 自分自身に住民税(所得割・均等割)が課税されます。
• 住民税の税率は自治体によりますが、一般的には収入額の10%程度(均等割は固定額)。
130万円の壁:社会保険加入義務のライン
対象:被扶養者(健康保険・年金で扶養されている人)
• 年収が130万円以下であれば、健康保険や厚生年金で「被扶養者」として扱われ、保険料を負担する必要がありません。
• 130万円を超えると、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
収入が130万円を超えるとどうなるか?
• 健康保険や厚生年金の保険料が発生します。保険料率は収入額に応じて決まるため、負担が大きくなる可能性があります。
• 家計全体で見ると、扶養者(例: 夫)の社会保険料負担が減る一方で、被扶養者(例: 妻)が自分で社会保険料を支払う形になります。
150万円の壁:対象は配偶者控除の影響
対象:配偶者控除の影響
• 年収が150万円以下であれば、扶養者(例: 夫)が配偶者控除(38万円)を満額受けられます。
• 年収が150万円を超えると、配偶者控除が段階的に減少し、201万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
各壁の影響の違い
壁の金額 関連する制度 主な影響
103万円 所得税 自分に所得税が課税される。扶養控除には影響なし。
108万円 住民税 自分に住民税が課税される。扶養控除には影響なし。
130万円 社会保険(扶養) 社会保険の被扶養者から外れ、自分で保険料を負担する必要がある。
150万円 配偶者控除 扶養者が受ける配偶者控除が減少する。
壁のまとめ【103万円・108万円・130万円・150万円】
• 103万円の壁:所得税が課税されるが、扶養控除には影響がないため、比較的負担は軽い。
• 108万円の壁:住民税が課税されるが、扶養控除には影響がない。
• 130万円の壁:社会保険料の負担が発生するため、手取り額への影響が大きい。
• 150万円の壁:扶養者の税制メリットが減少する。
各壁を意識することで、家計全体の税負担や手取り額を最適化できます。具体的な計算が必要な場合は収入や状況を教えていただければサポートします!
住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、住民税(市町村民税・都道府県民税)が課税されない世帯のことです。住民税は所得に応じて課税されるため、一定の要件を満たすと非課税となります。住民税非課税世帯になると、税金や社会保障制度での優遇を受けられることがあり、生活支援を受けるための基準ともなるため、重要な制度です。
1. 住民税が非課税となる条件
住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税を課税されない状態を指します。非課税となる要件は以下の通りです。
(1) 所得要件
次のいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。
1. 所得割が非課税
• 所得が、住民税の所得割課税基準額(課税標準額)以下である場合。
(例:2024年度基準で35万円 × 扶養人数 + 42万円が基準額)
2. 均等割が非課税
• 次のいずれかの条件を満たす場合、均等割も非課税となります:
• 生活保護を受給している場合。
• 合計所得が市町村が定める非課税限度額以下である場合。
(2) 非課税限度額の計算
住民税非課税限度額は以下の計算式で算出されます:
• 単身者(扶養なし):合計所得が43万円以下。
(例:基礎控除42万円+住民税の均等割課税額の最低基準)
• 扶養親族がいる場合:
• 非課税限度額=35万円 ×(扶養人数 + 1) + 10万円
(3) 特例措置
特定のケースでは、条件が緩和されることがあります。
• 高齢者(65歳以上):年金収入が公的年金控除を差し引いた後、住民税非課税基準内であれば、非課税対象になります。
2. 主な対象となる世帯
• 無収入または低所得世帯
• 高齢者世帯(公的年金のみで生活している場合)
• 生活保護を受給している世帯
• 一部障害者手帳保持者など
3. 住民税非課税世帯のメリット
住民税が非課税となることで、以下のような経済的な支援や優遇が受けられます。
(1) 国民健康保険料の軽減
• 国民健康保険料は所得に応じて計算されるため、住民税非課税世帯では大幅に減額されることがあります。
(2) 医療費負担の軽減
• 高額療養費制度の自己負担額が低くなり、医療費負担が軽減されます。
(3) 各種行政サービスの優遇
• 子育て支援(保育料の減免)
• 公営住宅の入居優先や家賃減額
(4) 給付金や特別支援金
• コロナ禍や物価高騰時には、住民税非課税世帯を対象とした給付金(例:特別定額給付金など)が支給される場合があります。
(5) 学費の軽減
• 非課税世帯の子どもが進学する際、授業料免除や奨学金の優遇が受けられることがあります。
(6) 公共料金の割引
• NHK受信料の減免など。
3. 住民税非課税世帯のメリット
住民税が非課税となることで、以下のような経済的な支援や優遇が受けられます。
(1) 国民健康保険料の軽減
• 国民健康保険料は所得に応じて計算されるため、住民税非課税世帯では大幅に減額されることがあります。
(2) 医療費負担の軽減
• 高額療養費制度の自己負担額が低くなり、医療費負担が軽減されます。
(3) 各種行政サービスの優遇
• 子育て支援(保育料の減免)
• 公営住宅の入居優先や家賃減額
(4) 給付金や特別支援金
• コロナ禍や物価高騰時には、住民税非課税世帯を対象とした給付金(例:特別定額給付金など)が支給される場合があります。
(5) 学費の軽減
• 非課税世帯の子どもが進学する際、授業料免除や奨学金の優遇が受けられることがあります。
(6) 公共料金の割引
• NHK受信料の減免など。
5. 具体的な非課税基準例(2024年度基準)
以下は、住民税が非課税になる年収の目安です(年金収入のみの場合を想定)。
家族構成 年収の目安
単身(65歳未満) 100万円以下
単身(65歳以上) 158万円以下
配偶者あり・扶養なし 156万円以下
配偶者あり・扶養1人 211万円以下
6. 住民税非課税世帯の確認方法
• 毎年6月ごろに届く住民税決定通知書で確認できます。
• 不明な場合は、お住まいの市区町村役場の税務課に問い合わせると詳細を確認できます。
まとめ
住民税非課税世帯は、収入が低い場合に該当し、税金や社会保険料、生活支援で多くの優遇を受けられます。ただし、家族全体の収入や控除対象を正確に把握し、必要に応じて市町村役場で手続きを行うことが重要です。
基礎控除について
基礎控除について
基礎控除は、所得税や住民税の計算において、所得から一定額を差し引くことができる控除のことです。この控除を受けることで、納める税金を減らすことができます。
なぜ基礎控除があるの?
人間が生活していくためには、ある程度の収入が必要です。基礎控除は、この最低限の生活を保障するための制度と言えます。つまり、誰もが一定の所得までは税金を払わなくても良い、という考えに基づいています。
基礎控除の金額は?
基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。2020年の税制改正により、基礎控除額は大幅に見直されました。
- 合計所得金額が2,400万円以下の方:
基礎控除額は48万円となります。 - 合計所得金額が2,400万円を超える方:
基礎控除額は、合計所得金額に応じて段階的に減額されます。
基礎控除を受けるには? - 確定申告:
自分で事業を行っている方や、給与所得以外に不動産所得などがある方は、確定申告を行う必要があります。確定申告の際に、基礎控除を申告することで、控除を受けることができます。 - 年末調整:
会社員の方などは、年末調整で基礎控除が適用されます。会社が手続きを行うため、特に自分で何かをする必要はありません。
基礎控除のメリット - 節税効果:
基礎控除を受けることで、納める税金を減らすことができます。 - 手続きの簡便さ:
年末調整の場合、会社が手続きを行うため、納税者が特別な手続きをする必要はありません。
注意点 - 基礎控除は毎年変更になる可能性がある:
税制改正により、基礎控除の金額や計算方法が変更になる場合があります。 - 所得状況によって控除額が変わる:
合計所得金額によって、基礎控除額が異なります。 - 確定申告が必要な場合がある:
全ての納税者が年末調整で済むわけではありません。確定申告が必要な場合は、自分で手続きを行う必要があります。
まとめ
基礎控除は、所得税や住民税の計算において、納税者が受けられる重要な控除の一つです。基礎控除を受けることで、納める税金を減らすことができます。
より詳しい情報を知りたい場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問 - 基礎控除と給与所得控除の違いは何ですか?
基礎控除は、納税者本人にかかる控除で、所得金額に応じて金額が異なります。一方、給与所得控除は、給与所得がある人が受けられる控除で、給与の額に応じて金額が異なります。 - 確定申告をしなくても基礎控除は受けられないのですか?
会社員の方など、年末調整で済む場合は、確定申告をしなくても基礎控除を受けることができます。 - 基礎控除は一生涯受けられますか?
はい、原則として一生涯受けられます。ただし、税制改正により、将来変更になる可能性はあります。
この回答は、一般的な情報に基づいて作成されたものです。より正確な情報を得るためには、税務署や税理士にご相談ください。
公的年金等控除とは?
公的年金等控除とは、年金収入から一定額を控除できる制度のことです。年金は所得として扱われますが、この控除によって、年金から得られる所得に対する税負担を軽減することができます。
なぜ公的年金等控除があるの?
年金は、老後の生活を支える重要な収入源です。しかし、年金収入が増えるにつれて、税金も増えてしまうと、生活が圧迫されてしまう可能性があります。そこで、年金受給者が安心して生活できるように、公的年金等控除が設けられています。
控除の仕組み
公的年金等控除の額は、年金の種類、金額、年齢、そして他の所得の有無などによって異なります。
一般的に、年金の種類や金額が多ければ多いほど、控除額も大きくなります。
控除を受けるためには
公的年金等控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、公的年金に関する書類や、他の所得に関する書類などを提出します。
控除のメリット
- 税負担の軽減: 年金所得に対する税負担を軽減することができます。
- 老後の生活の安定: 税負担が軽減されることで、老後の生活を安定させることができます。
注意点 - 確定申告が必要: 公的年金等控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
- 控除額は毎年変わる可能性がある: 税制改正などにより、控除額が変更になる場合があります。
- 他の所得との関係: 他の所得が多い場合、控除額が制限される場合があります。
まとめ
公的年金等控除は、年金受給者にとって非常に重要な制度です。確定申告を行うことで、税負担を軽減し、老後の生活を安定させることができます。もし、公的年金等控除について詳しく知りたい場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめします。
いです。
住民税の申告制度とは?
住民税の申告制度とは、市区町村に対して前年の所得を申告し、それに基づいて住民税(市町村民税・都道府県民税)が計算・課税される仕組みのことです。所得がある人は、所得税とは別に住民税の申告が必要な場合があります。
住民税とは?
• 住民税は、地方自治体(市区町村や都道府県)が住民サービスを提供するための財源です。
• 前年の所得に基づいて計算され、6月から翌年5月までの期間で支払います。
住民税の申告が必要な人・不要な人
申告が必要な人
次のような人は住民税の申告が必要になります。
1. 確定申告をしていないが所得がある人
• 会社員ではない個人事業主やフリーランス
• 年金を受給しているが、課税対象となる所得がある人
• アルバイトやパートで収入があるが確定申告をしていない人
2. 所得税の確定申告をする必要はないが、住民税の申告を求められる場合
• 年収103万円以下のアルバイト・パート(確定申告不要でも、自治体からの申告依頼が来ることがある)
• 所得税の非課税ライン内でも、住民税の非課税制度(例:均等割非課税)を適用するために申告が必要な場合
• 医療費控除や扶養控除を受けたいが、確定申告をしていない人
3. ふるさと納税のワンストップ特例を利用しなかった人
• ふるさと納税をしたが、確定申告もワンストップ特例の申請もしていない場合、住民税の申告が必要になることがある
申告が不要な人
• 所得税の確定申告をした人
• 確定申告をすると、その情報が自治体にも送られるため、住民税の申告は不要
• 給与所得者で、勤務先から年末調整後の給与支払報告書が自治体に提出される人
• 所得が全くない人(ただし、住民税非課税証明書が必要な場合は申告することを推奨)
住民税の申告方法
申告の流れ
1. 申告書を入手する
• 市区町村の役所(住民税課など)で入手、または自治体のWebサイトからダウンロード可能
2. 必要事項を記入
• 氏名・住所・マイナンバー
• 前年の収入・所得の内訳
• 各種控除(医療費控除、扶養控除、社会保険料控除など)
3. 必要書類を添付
• 給与所得や年金所得がある場合は源泉徴収票
• 控除を受ける場合は、領収書や証明書(医療費の領収書、生命保険の控除証明書など)
4. 提出する
• 市区町村の役所窓口へ持参
• 郵送で提出
• 一部の自治体ではオンライン申告(eLTAX)も可能
申告の期限
• 通常は毎年3月15日まで(確定申告と同じ)
• 自治体によっては多少異なる場合があるため、確認が必要
住民税の計算方法
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの部分から構成されます。
1. 均等割(一定額)
• 所得の多少にかかわらず、定額で課される税金
• 例)都道府県民税 1,500円 + 市区町村民税 3,500円 = 5,000円(標準)
• 東日本大震災の復興税として、2014年~2023年まで均等割が1,000円上乗せされていた(現在は終了)
2. 所得割(所得に応じて計算)
• 課税所得(収入-各種控除)に一定の税率をかけて計算
• 一般的な税率
• 市区町村民税:6%
• 都道府県民税:4%
• 合計:10%
計算例(年収300万円、給与所得控除後の課税所得150万円の場合)
1. 均等割:5,000円
2. 所得割:150万円 × 10% = 15万円
3. 合計:15万5,000円(均等割 + 所得割)
住民税の支払い方法
住民税の支払い方法には以下の2つがあります。
1. 特別徴収(給与天引き)
• 会社員の場合、会社が給与から天引きして自治体に納める
• 6月から翌年5月までの12回払い
2. 普通徴収(個人で納付)
• 個人事業主や無職の人などが、自分で納める方法
• 支払方法
• 6月、8月、10月、翌年1月の4回払い
• 一括納付も可能
• 口座振替、コンビニ払い、自治体によってはQRコード決済やクレジットカード払いも対応
まとめ
• 住民税は前年の所得に応じて課税される地方税で、確定申告をしていない人は住民税の申告が必要な場合がある
• 申告不要な場合でも、控除を受けたい人や非課税証明が必要な人は申告を検討
• 申告方法は役所への提出(窓口・郵送・オンライン)で、期限は通常3月15日
• 住民税は「均等割+所得割」で計算され、特別徴収(給与天引き)または普通徴収(個人払い)で納付
住民税の申告は、控除を受けたり証明書を取得するために大切な手続きです。不明点があれば自治体の住民税課に確認するとよいでしょう。
所得税の確定申告が終了した後、申告された内容が市町村に住民税等の計算に必要な数値として通達される時期
所得税の確定申告が終了した後、申告された内容が市町村に住民税等の計算に必要な数値として通達される時期は、おおよそ以下の通りです。
通達の時期
- 確定申告期間終了後、おおむね1ヶ月から2ヶ月程度:税務署から市町村へ確定申告で申告された内容が通知されます。
住民税の決定時期 - 市町村は、この通知に基づいて住民税の計算を行い、通常、5月から6月にかけて住民税額を決定します。
住民税の納税方法と通知時期 - 特別徴収(給与天引き)の場合:
- 勤務先を通じて、5月から6月頃に「特別徴収税額決定通知書」が配布されます。
- 住民税は、6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引きされます。
- 普通徴収(納付書払い)の場合:
- 6月頃に市町村から納税者本人宛に「納税通知書」が送付されます。
- 納税者は、通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します。
注意点 - 確定申告の時期や内容、市町村の処理状況によって、通知時期が多少前後する場合があります。
- 確定申告の内容に誤りがあった場合や、申告が遅れた場合などは、住民税の決定や通知が遅れることがあります。
より詳細な情報や個別の状況については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせいただくことをお勧めします。
国民健康保険料の金額は、住民税の決定より前に、ある程度の目安を知ることができます。ただし、正確な金額は住民税の決定後となります。
国民健康保険料の金額は、住民税の決定より前に、ある程度の目安を知ることができます。ただし、正確な金額は住民税の決定後となります。
国民健康保険料の計算の仕組み
- 国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。
- この所得情報は、確定申告や住民税申告によって市町村に伝えられます。
- 市町村は、この情報をもとに国民健康保険料を計算します。
国民健康保険料の通知時期 - 国民健康保険料の通知は、通常、6月中旬から7月頃に届きます。
- これは、住民税の決定通知とほぼ同時期、もしくは少し遅れて通知されることが多いです。
国民健康保険料の目安を知る方法 - 前年の所得に基づいて計算する:
- 国民健康保険料は、所得割、均等割、平等割などの要素で構成されています。
- お住まいの市町村のホームページなどで、これらの計算方法や料率を確認し、ご自身の前年の所得にあてはめて計算することで、おおよその金額を把握できます。
- 市町村の窓口で相談する:
- 市町村の国民健康保険担当窓口で、前年の所得状況などを伝えれば、おおよその保険料を試算してもらうことができます。
注意点 - 国民健康保険料の計算には、所得だけでなく、世帯の状況や年齢なども影響します。
- そのため、ご自身で計算した金額は、あくまで目安として捉え、正確な金額は市町村からの通知を待つようにしてください。
ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
【おさらい】年金から天引きされるもの
年金から天引きされる社会保険料や税金について、わかりやすくご説明します。
年金から天引きされるもの
年金から天引きされるのは、主に以下のものです。
- 税金
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
- 介護保険料
- 国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)
これらの天引きは、年金受給者の所得や年齢、居住地の状況によって異なります。
それぞれの詳細 - 所得税
- 所得税は、年金収入を含む所得に対して課される税金です。
- 一定以上の年金収入がある場合に天引きされます。
- 年金受給額や控除額によって税額が変わります。
- 住民税
- 住民税は、都道府県や市区町村に納める税金で、前年の所得に基づいて計算されます。
- 一定以上の年金収入がある場合に天引きされます。
- お住まいの地域や所得によって税額が変わります。
- 介護保険料
- 介護保険料は、介護保険制度を支えるための保険料です。
- 65歳以上の年金受給者は、原則として年金から天引きされます。
- 市区町村によって保険料が異なります。
- 国民健康保険料/後期高齢者医療保険料
- これらの保険料は、医療費を支えるための保険料です。
- 75歳未満の方は国民健康保険料、75歳以上の方は後期高齢者医療保険料が年金から天引きされる場合があります。
- それぞれの保険料は、市区町村や所得によって異なります。
天引きの条件と注意点 - 天引きされるかどうかは、年金の受給額やその他の所得、年齢、お住まいの地域などによって異なります。
- 年金からの天引きが中止され、納付書で自分で納める必要がある場合もあります。
- 税金や社会保険料の計算方法や詳細については、お住まいの市区町村や年金事務所にお問い合わせください。
参考情報 - 年金から天引きされるものとは?税金や社会保険料の計算方法を解説
- https://www.fp.au-financial.com/media/shisan/article-077.html
- 年金から引かれるものとは?計算方法や早見表でわかりやすく解説 – セゾンカード
- https://www.saisoncard.co.jp/topic/entry/sin_nisa_2405_2/
これらの情報を参考に、ご自身の年金から天引きされる金額について確認してみてください。
年金の「155万円の壁」と「211万円の壁」とは
年金の「155万円の壁」と「211万円の壁」について これらは、年金受給者の税金や社会保険料の負担額が変化する目安となる金額です。それぞれの壁について詳しく説明します。
155万円の壁
- この壁は、公的年金等に係る所得の計算方法に関係しています。
- 65歳未満の方の場合、年金収入が108万円を超えると所得税の課税対象となります。
- 65歳以上の方の場合、年金収入が158万円を超えると所得税の課税対象となります。
- しかし、公的年金等控除額が、155万円で変わるため、155万円が1つの目安とされています。
- つまり、年金収入が155万円を超えると、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。
211万円の壁 - この壁は、年金から天引きされる介護保険料に関係しています。
- 年金収入が年間211万円を超えると、介護保険料の負担が増えることがあります。
- これは、介護保険料の計算方法が、年金収入に応じて段階的に設定されているためです。
- ただし、介護保険料は市区町村によって異なるため、211万円はあくまで目安となります。
注意点 - これらの壁は、あくまで目安であり、個々の状況によって税金や社会保険料の負担額は異なります。
- 年金収入以外にも、他の所得がある場合や、控除額によっても負担額は変わります。
- 正確な金額については、お住まいの市区町村や年金事務所にご確認ください。
参考情報 - 年金受給額はいくらまでなら税金がかからない?年金にかかる税金について解説:
- https://dimes.jp/magazine/tax/230822_pension_tax
これらの情報を参考に、ご自身の年金収入と照らし合わせて、税金や社会保険料の負担額について確認してみてください。
国民健康保険計算機
このサイトで国民健康保険の試算ができます。
年齢と年収、住居地などを入力するだけです。

年金の繰上げ受給について
年金の繰上げのメリット・デメリット
確定申告(e-TAX)
税務署【国税庁】
デジタル庁

株を始めましょう (新NISAで益々有利に)
インフレ対策をしましょう。
【株の買い方】
【新NISA】
【新NISA お勧め10選】
お勧め書籍
本当の自由を手に入れる お金の大学 (改訂版) 両@リベ大学長

お金の大冒険
北の大地十勝
tokachi_sky (とかちスカイ)北の大地十勝 Kita-no-Daichi Tokachi







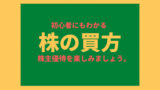

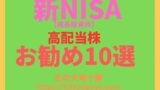


コメント