株の基本・上場・非上場・指値・成行・PER・PBR・ROE・ROA・配当金・利回り・損益通算・相殺・コモディティー(Commodity)とは

#投資用語集 #資産運用用語 #株式投資用語 #株の専門用語
- 株の専門用語を初心者向けに解説
- 株の基本
- 売買単位(単元)ばいばいたんい・たんげん
- 時価総額 (じかそうがく)
- 純利益(じゅんりえき)
- 営業利益(えいぎょうりえき)
- 経常利益(けいじょうりえき)
- ROE(自己資本利益率)じこしほんりえきりつ
- 自己資本比率(じこしほんひりつ)
- EPS(1株当たり利益)
- BPS(1株当たり純資産)
- 配当(はいとう)
- インデックス運用(いんでっくすうんよう)
- アクティブ運用(あくてぃぶうんよう)
- アクティブ運用(あくてぃぶうんよう)
- 分配金(ぶんぱいきん)
- 投資信託(とうししんたく)
- 株価の動きに関する用語
- 株の取引に関する用語
- 株価の分析に使う用語
- その他
- 損益通算・相殺について
- インデックス投資 (index investment)
- 高配当株(high dividend stocks)
- インデックス投資 VS 高配当株
- ディフェンシブ銘柄とは
- ROE
- ROA (Return on Assets)
- DOE(Debt to Equity Ratio、負債資本比率)とは
- ベータ
- テクニカル分析
- 株式投資におけるアクティビストとは
- アクティビストファンドとは
- コモディティー(Commodity)とは
- ファンダメンタル分析
- デリバティブ
- r > g(トマ・ピケティの法則)とは?
- 株式投資用語集(株式用語) まとめ
- まとめ
- チャットGPTを使っていますか?
- 新NISAについて
- 株を始めるには。
- 北の大地十勝(北海道)に移住
株の専門用語を初心者向けに解説
株の投資を始めるにあたって、様々な専門用語が出てきて戸惑う方も多いかと思います。ここでは、初心者の方でも理解しやすいように、基本的な用語を一つずつ解説していきます。
株の基本
株式: 会社が発行する所有権を表す証券です。株式を保有することで、その会社の株主となり、利益の一部(配当金)を受け取ったり、会社の経営に関与する権利を得たりすることができます。
株価: 株式が取引所で売買される際の値段のことです。需要と供給のバランスによって変動します。
株主: 株式を保有している人のことです。
上場: 株式を証券取引所に登録し、一般に売買できるようにすることです。
非上場: 上場されていない株式のことです。
売買単位(単元)ばいばいたんい・たんげん
単位と価格
* 売買単位(単位): 株を買ったり売ったりする時の、会社の決めた最低単位のことです。たとえば、「100株単位」なら、一度に買う株数は100株、200株、300株…となります。
* 株式: 会社が発行する所有権のことで、株主になると会社の所有者のひとりになれます。
時価総額 (じかそうがく)
* 時価総額: 会社全体の価値を示すもので、発行されているすべての株に、その時の株価をかけたものです。
純利益(じゅんりえき)
会社が事業で儲けたお金から、かかった費用や税金などをすべて引いた、最終的な利益のことです。
営業利益(えいぎょうりえき)
会社の本業で儲けた利益のことです。本業の儲けが大きいほど、会社の事業がうまくいっていると言えます。
経常利益(けいじょうりえき)
会社全体の活動から得られた利益のことです。本業の利益に、預金の利息や土地の売却益など、本業以外で得た利益も足したり引いたりして計算します。
ROE(自己資本利益率)じこしほんりえきりつ
会社が株主から集めたお金(自己資本)を使って、どれだけ効率よく利益を出せたかを示す指標です。この数字が高いほど、お金を上手に使って儲けている会社と言えます。
自己資本比率(じこしほんひりつ)
会社の安定性を示す指標で、返済の必要がない自分たちのお金が、全体の資金のうちどれくらいの割合を占めているかを示します。
EPS(1株当たり利益)
純利益を発行済みの株数で割ったもので、株1つあたりどれだけの利益を出したかを示します。
BPS(1株当たり純資産)
会社の持っている資産を、発行済みの株数で割ったものです。この数字が高いほど、会社の解散時などに株主に戻ってくるお金が多いと考えられます。
配当(はいとう)
会社が出した利益を株主に分配することです。配当金として、お金が支払われることが一般的です。
インデックス運用(いんでっくすうんよう)
特定の市場の動き(例:日経平均株価やTOPIX)と同じような値動きを目指して投資することです。個別の株を選ぶのではなく、市場全体に分散して投資するスタイルです。
アクティブ運用(あくてぃぶうんよう)
市場平均を上回る成果を目指して、積極的に投資することです。専門家が銘柄の選択や売買タイミングを判断します。
アクティブ運用(あくてぃぶうんよう)
市場平均を上回る成果を目指して、積極的に投資することです。専門家が銘柄の選択や売買タイミングを判断します。
分配金(ぶんぱいきん)
投資信託が投資家に出資額に応じて分配するお金のことです。株式の配当金に似ています。投資信託が投資家に出資額に応じて分配するお金のことです。株式の配当金に似ています。
投資信託(とうししんたく)
投資家から集めたお金をひとまとめにして、専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。
株価の動きに関する用語
値上がり: 株価が上昇することです。
値下がり: 株価が下落することです。
高値: ある期間における株価の最高値のことです。
安値: ある期間における株価の最安値のことです。
始値: 取引開始時の株価のことです。
終値: 取引終了時の株価のことです。
株の取引に関する用語
売買: 株式を売ったり買ったりすることです。
注文: 株式の売買を証券会社に指示することです。
指値: 自分が希望する価格で売買する注文のことです。
成行: 現在の市場価格で売買する注文のことです。
手数料: 株式の売買を行う際に証券会社に支払う手数料のことです。
株価の分析に使う用語
PER (株価収益率): 株価が1株当たりの利益の何倍になっているかを示す指標です。PERが低いほど割安と判断されることが多いです。
PBR (株価純資産倍率): 株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。PBRが1倍を下回ると、株価が純資産よりも安いと判断されることがあります。
ROE(自己資本利益率)じこしほんりえきりつ:
会社が株主から集めたお金(自己資本)を使って、どれだけ効率よく利益を出せたかを示す指標です。この数字が高いほど、お金を上手に使って儲けている会社と言えます。
配当金: 会社が利益の一部を株主に分配するお金のことです。
配当利回り: 配当金が株価に対してどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
その他
株指数: 複数の銘柄の株価の動きを平均化した指数のことです。日経平均株価などが代表的です。
投資信託: 複数の投資家が資金を出し合って、プロの運用者に運用してもらう投資商品です。
ETF: 上場投資信託の略で、株指数などに連動する投資信託のことです。
損益通算・相殺について
同じ証券会社の同日取引において、含み益のあるA社の株と含み損のあるB社の株を取引した場合の税務上の扱いは、以下のようになります。
原則
- 損益通算: 同日中に同一の証券会社で、譲渡益(含み益を実現させた利益)と譲渡損(含み損を実現させた損失)が生じた場合、その損益は通算されます。
- 相殺: A社の含み益とB社の含み損は相殺され、最終的な損益額に対して課税額が計算されます。
例 - A社株式の譲渡益:10万円
- B社株式の譲渡損:5万円
この場合、A社の10万円の利益とB社の5万円の損失が相殺され、課税対象となるのは差額の5万円となります。
注意点 - 同一証券会社: 損益通算は、同一の証券会社内での取引に限られます。異なる証券会社間での損益通算はできません。
- 同一日: 損益通算は、同一日に行われた取引に限られます。異なる日の取引では損益通算はできません。
- 特定口座: 特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、証券会社が自動的に損益通算を行い、源泉徴収税額を調整します。
- 一般口座: 一般口座で取引している場合は、確定申告で損益通算を行う必要があります。
詳細 - 株式譲渡益課税: 株式の譲渡益には、一律20.315%(所得税15.315%+復興特別所得税0%+住民税5%)の税金がかかります。
- 年間取引報告書: 証券会社から年間取引報告書が送付されますので、確定申告の際に利用してください。
インデックス投資 (index investment)
インデックス投資とは、特定の株価指数(日経平均株価、S&P500など)の動きに連動するように、その指数を構成する全ての銘柄、または代表的な銘柄に分散投資を行う方法です。
メリット
* 市場全体の成長に便乗できる: 個別銘柄の分析は不要で、市場全体に投資することで、市場が成長すれば、それに合わせて資産も増える可能性が高いです。
* コストが低い: アクティブファンドと比較して、管理費用が低い傾向にあります。
* 長期的な視点で安定的なリターン: 短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で資産形成に取り組めます。
デメリット
* 市場全体の動きに左右される: 市場が下落すると、投資額も減少します。
* 個別銘柄の成長を捉えられない: 個別銘柄が大きく成長した場合、その成長分を享受できません。
高配当株(high dividend stocks)
高配当株とは、他の株式と比較して、高い配当金を得られる株式のことです。配当金は、企業が得た利益を株主に分配するもので、いわば株主への「おこづかい」のようなものです。
メリット
* 安定的な収入源: 定期的に配当金を受け取れるため、安定的な収入源となります。
* 株価の下落をある程度カバー: 株価が下落した場合でも、配当金を受け取れることで、損失をある程度カバーできる可能性があります。
デメリット
* 成長性は低め: 一般的に、高配当株は安定した収益を重視するため、成長株に比べて成長性は低い傾向にあります。
* 企業の業績悪化リスク: 企業の業績が悪化すると、配当が減額される可能性があります。
インデックス投資 VS 高配当株
どちらを選ぶべきかは、個人の投資目標やリスク許容度によって異なります。
* 長期的な資産形成を目指す方: インデックス投資は、長期的な視点で安定的に資産を増やしたい方に向いています。
* 安定的な収入を得たい方: 高配当株は、定期的な配当金を受け取りたい方に向いています。
重要なのは、どちらか一方にこだわるのではなく、両方の特徴を理解し、ご自身の投資スタイルに合った方法を選ぶことです。
ディフェンシブ銘柄とは
ディフェンシブ銘柄とは、景気の変動の影響を受けにくく、業績が安定している業種の銘柄を指します。
- 主に生活必需品である食品、医薬品、社会インフラである電力・ガス、鉄道、通信といった業種が挙げられます。
- 景気が後退しても業績がそれほど悪化せず、「守り」に強いことから、こう呼ばれています。
- ディフェンシブ銘柄は、一般的に株価の変動幅が小さく、安定した収益が期待できます。
- 一方で、景気上昇局面では、他の景気敏感株に比べて株価の上昇が緩やかになる傾向があります。
ディフェンシブ銘柄のメリット - 景気変動に左右されにくく、業績が安定している
- 株価の変動幅が小さく、安定した収益が期待できる
- 比較的安全な投資対象
ディフェンシブ銘柄の注意点 - 景気上昇局面では、他の景気敏感株に比べて株価の上昇が緩やか
- 大きな利益は期待できない
主なディフェンシブ銘柄の例 - 食品:キッコーマン、味の素、サントリー食品インターナショナル
- 医薬品:武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共
- 電力・ガス:東京電力ホールディングス、関西電力、大阪ガス
- 鉄道:JR東日本、JR東海、JR西日本
- 通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
投資判断のポイント - ディフェンシブ銘柄は、一般的に株価の変動幅が小さく、安定した収益が期待できます。
- しかし、景気上昇局面では、他の景気敏感株に比べて株価の上昇が緩やかになる傾向があります。
- 投資を行う際は、企業の業績や財務状況などをしっかりと分析し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて判断することが重要です。
ROE
ROE: Return on Equityの略。株主資本利益率とも呼ばれ、株主資本に対する当期純利益の割合を示します。株主から見た収益性を測る指標です。
ROA (Return on Assets)
ROA: Return on Assetsの略。総資産利益率とも呼ばれ、総資産に対する当期純利益の割合を示します。企業全体の収益性を測る指標です。
DOE(Debt to Equity Ratio、負債資本比率)とは
DOE(負債資本比率)とは、企業の財務構造を分析するための指標の一つで、企業の負債と自己資本の割合を示します。
DOEの計算式
- DOE(負債資本比率)= 総負債 ÷ 自己資本
DOEからわかること - 財務レバレッジ: DOEが高いほど、企業が事業活動に必要な資金を負債に頼っている割合が高いことを示します。これは、財務レバレッジが高い状態と言えます。
- 財務リスク: 一般的に、DOEが高いほど企業の財務リスクは高まると考えられます。なぜなら、負債が多いほど利息の支払いが増え、業績が悪化した場合に返済が困難になる可能性があるからです。
- 企業の成長性: 一方で、DOEが高いことが必ずしも悪いわけではありません。企業が成長期にある場合、積極的に資金を借り入れて事業を拡大することがあります。この場合、DOEが高くても将来的な成長が見込めるため、投資家にとって魅力的な投資対象となることもあります。
DOEの解釈 - 業界平均との比較: DOEを評価する際は、同業他社のDOEと比較することが重要です。業界平均よりもDOEが高い場合は、財務リスクが高い可能性があります。
- 企業の過去の推移: 企業の過去のDOEの推移を見ることで、財務状況がどのように変化してきたかを把握できます。DOEが上昇傾向にある場合は、財務リスクが高まっている可能性があります。
- 企業の規模や業種: DOEの適切な水準は、企業の規模や業種によって異なります。一般的に、成熟した大企業はDOEが低く、成長中のスタートアップ企業はDOEが高い傾向があります。
DOEを活用した投資判断 - DOEは、企業の財務状況を把握するための重要な指標の一つですが、これだけで投資判断を行うことは避けるべきです。
- 他の財務指標(例:自己資本比率、流動比率、当座比率など)や、企業の業績、成長性、キャッシュフローなどを総合的に判断することが重要です。
まとめ - DOE(負債資本比率)は、企業の財務構造を分析するための重要な指標の一つです。
- DOEが高いほど財務レバレッジが高く、財務リスクも高まる可能性があります。
- DOEを評価する際は、業界平均との比較、過去の推移、企業の規模や業種などを考慮する必要があります。
- DOEは投資判断の材料の一つであり、他の財務指標や企業の情報を総合的に判断することが重要です。
ベータ
ベータ: 個々の株式の価格変動が市場全体の価格変動に対してどれくらい連動しているかを示す指標です。ベータが1を超えると市場平均よりも変動が大きく、1を下回ると市場平均よりも変動が小さいとされます。
テクニカル分析
テクニカル分析: 株価の過去の動きやチャートパターンから将来の株価を予測しようとする分析方法です。移動平均線、RSI、MACDなどが代表的なテクニカル指標です。
株式投資におけるアクティビストとは
株式投資におけるアクティビストとは、企業の株式を一定程度保有し、その企業の経営陣に対して積極的に働きかけ、企業価値の向上を目指す投資家のことです。
アクティビストの主な活動内容
- 経営陣との対話・交渉
- 株主提案権の行使
- 委任状勧誘
- 株式の買い増し
- メディアを通じた広報活動
アクティビストの目的
アクティビストの主な目的は、以下の通りです。 - 企業価値の向上
- 株主利益の最大化
- 経営効率の改善
- 不正行為の是正
アクティビストのメリット・デメリット
メリット - 企業価値の向上
- 株主利益の増加
- 経営の効率化
- コーポレートガバナンスの強化
デメリット - 経営陣との対立
- 短期的な利益追求
- 企業の混乱
- 風評被害
アクティビストの事例 - 村上ファンド
- スリー・ポイント
- エリオット・マネジメント
- ポールソン・アンド・カンパニー
アクティビストへの投資
アクティビストの活動に賛同する場合、その企業への投資を検討するのも一つの方法です。しかし、アクティビストの投資戦略は、リスクも伴うため、十分な情報収集と分析が必要です。
まとめ
アクティビストは、企業の経営に積極的に関与し、企業価値の向上を目指す投資家です。アクティビストの活動は、企業に良い影響を与えることもありますが、 негаティブ な影響を与えることもあります。アクティビストへの投資を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、慎重に判断する必要があります。
注意: - アクティビストに関する情報は、常に変化しています。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
- アクティビストの中には、悪質な投資家も存在します。注意が必要です。
アクティビストファンドとは
アクティビストファンドとは、投資先の企業価値を高めるために、積極的に経営に関与する投資ファンドのことです。具体的には、以下のような活動を行います。
主な活動内容
- 株主提案: 株主総会で、配当金の増加、自社株買い、経営陣の刷新、組織再編などの提案を行う。
- 経営陣との対話: 経営陣と直接対話し、経営改善を求める。
- 公開書簡: 企業の経営方針や改善策について、公開書簡を通じて意見表明を行う。
- 委任状争奪: 株主総会で、自身の提案を支持する株主を募るために、委任状争奪を行う。
アクティビストファンドの目的 - 主な目的は、投資先の企業価値を高め、株価を上昇させることで、投資リターンを得ることです。
- 企業価値が割安に評価されている企業や、経営に改善の余地がある企業を投資対象とすることが多いです。
アクティビストファンドの特徴 - 従来の投資ファンドが長期的な成長を待つスタンスであるのに対し、アクティビストファンドは短中期的に積極的な行動を起こします。
- 「物言う株主」とも呼ばれ、企業の経営に積極的に関与することが特徴です。
- 近年では、株主の発言力が増している傾向にあり、アクティビスト・ファンドの提言が企業の将来に大きな影響を与えることも少なくありません。
アクティビストファンドのメリット・デメリット - メリット
- 企業の経営改善を促し、企業価値を高める効果が期待できます。
- 株主にとって、より良いリターンを得る機会が増える可能性があります。
- デメリット
- 短期的な利益を追求するあまり、企業の長期的な成長を損なう可能性がある。
- 経営陣との対立が激化し、企業の安定性を損なう可能性がある。
代表的なアクティビストファンド - エリオット・マネジメント
- サード・ポイント
- バリューアクト・キャピタル
- ストラテジック・キャピタル
アクティビストファンドの活動は、企業の経営に大きな影響を与える可能性があり、近年、日本でもその存在感が増しています。
コモディティー(Commodity)とは
**コモディティー(Commodity)**とは、一般に「商品」を指しますが、経済や投資の文脈では特に 原材料や一次産品 のことを指します。
コモディティーの特徴
• 均一性(同質性):どの生産者のものでも品質に大きな違いがない(例:金、原油、小麦など)。
• 市場での取引:主に 商品先物市場 で売買される。
• 価格変動が大きい:需給や経済情勢に左右されやすい。
コモディティーの主な種類
1. エネルギー系:原油、天然ガス、石炭
2. 金属系:金、銀、銅、アルミニウム
3. 農産物系:小麦、トウモロコシ、大豆、コーヒー、綿
4. 畜産系:牛肉、豚肉
コモディティー化(コモディティ化)とは?
製品やサービスが 差別化を失い、価格競争に陥ること を指します。
例えば、スマートフォンや家電などで機能の違いが少なくなり、価格だけで選ばれるようになる現象がこれに当たります。
投資対象としてのコモディティーも注目されており、特に インフレ対策 や リスク分散 の目的で取引されることが多いです。
安定資産として『金ゴールド・GOLD』はコモディティーの代表的です。純金積立などもありますが管手数料などのコストを考慮しないといけません。もちろんキャピタルゲインの可能性はありますがインカムゲイン(利息)はないので、バランスが必要です。
ファンダメンタル分析
ファンダメンタル分析: 企業の財務状況、業績、業界動向などを分析し、企業の intrinsic value(本来の価値)を評価する方法です。DCF法などがこれに当たります。
デリバティブ
デリバティブ: 先物取引、オプション取引など、原資産(株式、債券など)の価格変動によってその価値が変動する金融商品のことです。
r > g(トマ・ピケティの法則)とは?
フランスの経済学者 トマ・ピケティ(Thomas Piketty) が『21世紀の資本(Le Capital au XXIe siècle)』で提唱した法則で、 「資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回ると、富の格差が拡大する」 という理論です。
用語の説明
• r(資本収益率):資本(貯蓄・投資)から得られる利益の割合。
• 例:株式投資や不動産運用で年5%の利益を得る場合、r = 5%
• g(経済成長率):GDP(国内総生産)などで測る経済全体の成長率。
• 例:日本の経済成長率が年2%なら、g = 2%
r > g の意味
• もし r(資本収益率)> g(経済成長率) なら、
→ 資本(資産)を持つ人はどんどん富を増やし、持たない人との格差が拡大する
• 逆に r ≤ g なら、
→ 経済成長が労働者の収入増につながり、格差は縮小しやすい
具体例
資産を持つ人(富裕層)
• 1億円を投資し、年5%(r = 5%)の利益 → 年500万円の収益
• その収益を再投資し続けると、富は雪だるま式に増える
資産を持たない人(労働者)
• 労働収入のみ(年収500万円、成長率 g = 2%)
• 経済が成長しても、給料は緩やかにしか増えない
結果として、富裕層と労働者の格差がどんどん広がる ことになる。
ピケティの主張
• 歴史的に、r > g の状態が多くの時代で成立していた
• 特に 19世紀のヨーロッパ(貴族・資本家 vs 労働者) や 21世紀の現代(富裕層 vs 一般庶民) で顕著
• 格差を是正するには、富裕層への課税(累進課税、相続税強化)などが必要
まとめ
✅ r > g のとき、資産を持つ人がより豊かになり、格差が拡大する
✅ 現代でもこの傾向が続いており、社会問題になっている
✅ 解決策として、税制改革や富の再分配が議論されている
ピケティの法則は、単なる経済理論ではなく、「なぜ格差が広がるのか?」 を説明する重要な概念として注目されています。
株式投資用語集(株式用語) まとめ
株式用語
- 売買単位(単元): 株式を売買する際の単位となる株式数。国内株式は100株で統一されている(国内上場の外国株式やETF、REITなどは除く)。
- 時価総額: 株価に発行済み株式数(普通株式数を用いるのが一般的)を掛けて算出。企業の市場価値・規模を金額で表したもの。
- PER(株価収益率): 株価をEPS(1株利益)で割った数値。株価と収益力とを比較することで、割高・割安を判断する際に利用される投資尺度。一般的には当期利益の予想値を計算に用いる。
- PBR(株価純資産倍率): 株価をBPS(1株当たり純資産)で割った数値。株価と純資産とを比較することで、割高・割安を判断する際に利用される投資尺度。基準の値は1。一般的には純資産の実績値を計算に用いる。
- 配当利回り: 1株当たり年間配当金を株価で割って算出。株価と配当金とを比較することで、割高・割安を判断する際に利用される投資尺度。一般的には当期年間配当金の予想値を計算に用いる。
- ROE(自己資本利益率): 純利益を自己資本(株主資本)で割って算出。株主が出したお金(資本)を使って、企業が最終的にどれだけ稼いでいるかを見る指標。ROE=PBR÷PERの関係がある。
- 自己資本比率: 自己資本を総資産で割って算出。企業の財務の安定性を見る代表的な指標。
- 売上高: 商品を売る、サービスを提供するなど、企業の主たる営業活動によって得た代金の総額。企業や業種により営業収益、経常収益などと表示する場合もある。
- 営業利益: 売上高から売上原価、販売費および一般管理費などの諸経費を引いた後の利益。本業でどれだけの利益を稼ぐかを示す。
- 経常利益: 営業利益に受取利息や配当金、支払金利などの営業外収支を加味した利益。企業の期間損益の推移を見たり、企業同士の実力を比べたりするのに良く用いられる。
- 純利益: 経常利益に、通常の企業活動以外で発生した特別損益、法人税負担などを加味した利益。企業の経営活動の純粋な成果。当期利益、最終利益、税引き利益などとも呼ぶ。
- 営業利益率: 営業利益を売上高で割って算出。本業の稼ぐ力を表し、値が大きいほど稼ぐ力が強いことを示す。売上高営業利益率とも呼ぶ。
- 損益計算書(PL): 財務諸表の一つで、企業の一会計期間における経営成績を示す。英語表記「Profit and Loss statement」の略でPLとも呼ぶ。
- 貸借対照表(BS): 財務諸表の一つで、企業の一定時点における資産、負債、資本などの状況を示す。「Balance Sheet」の略でBSとも呼ぶ。
- キャッシュフロー計算書(CF): 財務諸表の一つで、企業の一会計期間における現金の出入りを示す。英語表記「Cash Flow statement」の略でCFとも呼ぶ。以下の3つの区分に分けて表示される。
- 営業キャッシュフロー: 商品の販売やサービスの提供で得た収入から、原材料購入などの支出を差し引いた現金収支。
- 投資キャッシュフロー: 設備投資や出資、資金貸し付け、投資有価証券の取得・売却などによる現金収支。
- 財務キャッシュフロー: 借り入れの増減など財務活動での現金収支。
- 権利確定日: 配当、株主優待、議決権など株主としての様々な権利が確定する日のこと。権利を得るためには権利確定日の2営業日前の権利付き最終日までに株式を購入する必要がある。権利付き最終日の翌営業日を権利落ち日と呼ぶ。
投資信託用語- 純資産総額: 投信に組み入れられている株式や債券などを時価評価し、その資産総額から投信の運営に必要な費用などを差し引いたもの。投信が運用する資産の規模を表す。
- 基準価額: 純資産総額を総口数で割って算出される投信の価格(口は投信の取引を行う際の単位)。多くの投信は1口1円で運用が開始され、1万口当たりの基準価額を1日1回算出して公表している。
- 分配金: 投信の決算に併せて投資家に支払われるお金。投信の運用資産の一部から支払われるため、純資産総額と基準価額はその分減少(下落)する。投信の分配方針によって支払いの頻度や金額は様々。
- 販売手数料: 投信の購入時にかかる手数料。投信によりゼロから4%程度までと幅がある。同じ投信でも、販売会社や買い方によって販売手数料が異なる場合がある。
- 信託報酬: 投信の保有中にかかる運用手数料に当たるコスト。純資産総額、基準価額の変動にはこのコスト分も含まれている。
- 信託財産留保額: 投信の解約時にかかるコスト。投信により異なり、ゼロから0.3%程度が一般的。
- インデックス運用: 株式や債券、商品などの市場全体の動きを示す指数(日経平均株価やダウ工業株30種平均、FTSE世界国債インデックスなど)に連動することを目指す運用スタイル。このタイプの投信をインデックス型投信と呼ぶ。
- アクティブ運用: 指数を上回る投資成果や絶対的なリターンが得られるように、投資先や売買のタイミングをファンドマネージャー・運用チームが随時判断していく運用スタイル。このタイプの投信をアクティブ型投信と呼ぶ。
- 運用会社: 投信の運用方針や商品内容を決定し、資産の実質的な運用(投資判断、組み入れ銘柄の選定、売買の指示など)を行う会社。
- 販売会社: 投信を募集・販売している会社。証券会社や銀行、信用金庫、郵便局など。一部の運用会社では、自社が運用する投信を個人に直接販売しているケースもある。
- ETF(上場投信): 上場株式と同じように証券取引所で売買できるインデックス型投信。
- REIT(不動産投信): 不動産を運用対象とする投信で、上場株式と同じように証券取引所で売買できる。オフィスビルや賃貸マンションなどに投資し、賃貸収入・売却益などの収益から管理費。支払金利などの費用を差し引いた利益の大半を投資家に分配する仕組み。
まとめ
- 株式投資は元本保証ではありません。 損失が出る可能性も十分に考慮する必要があります。
- 投資は自己責任で行ってください。 証券会社や金融機関のアドバイスは参考程度にし、最終的な判断はご自身で行ってください。
チャットGPTを使っていますか?
使いこなしたら、凄く便利ですよ。
私もブログ作成に協力していただいております。感謝!
新NISAについて
株を始めるには。
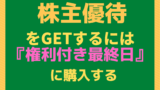
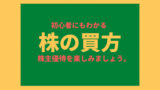

北の大地十勝(北海道)に移住

tokachi_sky (とかちスカイ)北の大地十勝 Kita-no-Daichi Tokachi

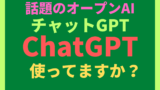

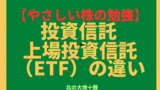
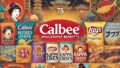

コメント